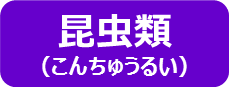| ■オオマドボタル |
ホタルの仲間ですが光りません。幼虫は陸上でカタツムリを食べています。
珍しい種類のようですが、福岡県南部では久留米市、八女郡黒木町、八女郡矢部村で採集しています。人手のあまり入らない自然林的な環境に生息しています。
6月中旬から7月上旬に成虫が見られます。雌は成虫になっても幼虫型のままだそうです。 |

左からオオマドボタル(雄)、ゲンジボタル、ヘイケボタル
 |
 |
| 頭部に透明な窓があり、窓蛍(マドボタル)の名前の由来です。 |
東南アジアには巨大なマドボタルが生息します。 (左)日本産オオマドボタル雄成虫(右)ボルネオ島産のマドボタル雌 |

|
| ■サツマニシキ |
福岡県南部の清水山で、暖かい地方に育つヤマモガシ(ヤマモガシ科)と言う樹木に小 さな穴がたくさん開いた葉がありました。捜してみると怪獣映画に出てくるような幼虫が見つかりました。やがて葉を折り曲げて繭を作り、成虫が羽化しまし た。サツマニシキ(マダラガ科)です。漢字で書くと「薩摩錦」で、その名の通り蛾の中では綺麗な翅をもっています。この蛾も熱帯・亜熱帯地方が主な生育地 のため、寒さは苦手です。福岡県内では普通は冬を越せないようで、この場所でも翌年には見られなくなりました。
マダラガ科の幼虫の中には有毒なものもあります。サツマニシキの幼虫は刺激を与えると、毛の先に丸く液体を出しました。毒があるのかな?思い切って腕にこ の液体を付けてみました。幸い腫れたりせず何事もありませんでした。他の人はどうでしょうか。頼んでいますが、まだ新たに実験に協力してくれる人は現れま せん。 |

ヤマモガシの被害葉 |

サツマニシキ幼虫 |

葉を巻いた繭 |

サツマニシキ成虫 |

|
| ■ヤマトタマムシ |
写真のヤマトタマムシ(タマムシと呼ばれている昆虫はヤマトタマムシというのが正式の名称です。)は、9月の上旬に当森林林業技術センターの敷地内で見つけました。
ヤマトタマムシの成虫は7~8月頃に発生します。そして、サクラ・ケヤキ・カシ・エノキなどの枯れ木に産卵します。産卵から2~3年後の初夏に枯れ木の中で蛹化します。そして、蛹化から約2~3週間後に成虫になります。
全体に緑色の金属光沢があり、背中に虹のような赤と緑の縦じまが入る、美しい昆虫です。この美しい翅(はね)を集めて作られたものに、奈良県の法隆寺というお寺につたわる「玉虫厨子」というものがあります。厨子とは仏像などを安置するものです。 |

Chrysochroa fulgidissima |

|
| ■虫えい |
「虫えい」とは、昆虫が植物に卵を産み付けることなどにより、植物の組織が異常な発達を起こしてできる「こぶ状」のものです。
左の写真は、ケヤキの葉の上にケヤキハフクロフシという袋状の「虫えい」ができている状態です。これは、タマワタムシ科のケヤキヒトスジワタムシという昆虫が卵を産みつけて出来たものです。
右の写真は、エゴノキの枝先にできた「虫えい」で、エゴノネコアシと呼ばれています。これは、ヒラタアブラムシ亜科のエゴノネコアシアブラムシという昆虫の幼虫が春先に、側芽に住み着くことでできます。
このように、植物や虫の組み合わせで、いろいろな「虫えい」があります。
五倍子(ごばいし)と呼ばれる、ヌルデの葉の「虫えい」のように、その中に含まれるタンニンがインクの原料として利用されるものもあります。 |
 |
 |
| ケヤキハフクロフシ (欅葉袋倍子) |
エゴノネコアシ (えごの猫足) |
|
 |
![]()
![]()
![]()
![]()